ここ数年、企業活動においてサステナビリティの重視・地球環境への配慮が求められるようになったのはもはや周知の事実である。廃棄物が発生しない製品生産を行い、原材料や製品を循環させる「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」を実現する仕組みは欧州を中心に浸透しつつある。東京財団研究所 主席研究員を務める平沼光氏は、著書『資源争奪の世界史』(日本経済新聞出版社)で欧州のサーキュラーエコノミー政策は「廃棄物を再資源化→流通」を目標としているのに対し、日本は「再資源化」で止まっていると指摘。平沼氏に、「日本発のグリーンシフト」の可能性を伺った。
EU諸国が新たな「資源国」になる?
──上梓された『資源争奪の世界史』は、各時代において主流だった資源を振り返りつつ、これからの時代の資源を考えるという内容になっています。平沼さんの考える「資源」の定義について、あらためて伺えますでしょうか。
平沼:「資源」と聞くと、石油や石炭といった地下に埋蔵されたエネルギーを生み出す物質をイメージする方が多いと思います。そうした固定観念を捨ててもらいたくて、本書では大航海時代の「香辛料」を資源の一例として紹介しました。私が考える資源の定義とは、「人々が求める利便性を備えているもの」であり、かつ「誰もが適切な価格でアクセスできるもの」です。実際石油や石炭も、安定的に採掘や加工、流通ができるようになって初めて「資源」とみなされるようになったのです。

──なぜ、そのような資源の再定義が必要になるのでしょうか。
平沼:今まさに、従来のイメージでは捉えきれない新しいタイプの資源が登場しつつあるからです。本書でも取り上げた「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」における廃棄物などはその良い例と言えるでしょう。これまでの経済モデルが地中から掘り出した天然資源を使って製品を「つくる→使う→捨てる」という資源を一方向で消費する経済モデルであったのに対し、サーキュラーエコノミーは、使い終わって廃棄物となった製品を再利用したり、廃棄物から原材料を回収して再び製品を生産するなど、生産・消費・再資源化のサイクルを循環させる経済のあり方です。レアアースなどのレアメタルをはじめとする貴重な天然資源の浪費を防ぎ、廃棄物の処理に伴う環境負荷を削減しようという狙いがあります。これは要するに、ごみ(廃棄物)を「資源」として再発見しようという考え方なのです。
ただ、こう説明すると、いかにもエコで自己犠牲的な感じがしますよね。日本でも、まだ「経済活動よりも地球環境を優先する」といったイメージが強いでしょう。しかしEUの資料などを見てみると、「サーキュラーエコノミーでGDPを7%アップさせる」、「EUに雇用を創出する」、「新たなビジネスの機会を生み出す」といったことが書かれています。要するにEUにおいては、サーキュラーエコノミーはむしろ「競争力をもたらす新たなビジネス」として捉えられていて、だからこそ普及が急速に進んでいるのです。
これからは、「資源」のあり方も大きく変わります。「再資源化された再生資源、あるいは再資源化が可能な資源を原材料に用いなければならない」というルールができれば、従来の石油や石炭、天然ガスといった埋蔵資源は相対的に価値が低くなる。これまで資源国といえば産油国でしたが、これからは「再生資源」を生み出せる国が資源国になります。つまり、EUは、サーキュラーエコノミーを実現する体制をいち早く整えることで、新たな資源国になろうとしているのです。国内の廃棄物をいかに再資源化し、海外に依存している天然資源の輸入量を抑えるかは、日本にとっても大きな問題です。
ボトムアップで再資源化の体制を構築
──現状、日本において再生資源の活用が遅れてしまっている理由を教えてください。
平沼:理由は大きく2つあります。1つは、リサイクル関連の法案が細かく分かれすぎていること。もう1つは、Waste Management(北米)やVEOLIA(フランス)、SUEZ(フランス)、umicore(ベルギー)のような巨大な廃棄物処理企業、いわゆるメガリサイクラーが存在しないことです。
まず、リサイクル関連法案について説明します。現状の法律では、「資源循環法」という大きな法律の下に、6つの品目ごとのリサイクル法がぶら下がる形となっています。「家電」「食品」「容器」「建築」「自動車」「小型家電」という6つの品目です。
この細分化の問題点は、この項目から漏れたものはそもそもリサイクルされないことです。また、それぞれの品目ごとに体制が構築されているため、リサイクル産業そのものが大きくなりづらいという問題もあります。再資源化の法的な要請も、あくまでも「廃棄物を循環利用“できる状態にすること”」という準備行為にとどまり、実際にどれだけ再利用されているかをチェックする規定はありません。総じて現状の資源循環法は、サーキュラーエコノミーではなくあくまでもリニアエコノミーを前提としたものなのです。
欧州では、各分野の生産者、利用者がそれぞれのフェーズで排出する廃棄物を、大規模にリサイクルを手がけるメガリサイクラーが一手に引き受ける構造になっています。メガリサイクラーは、回収から再生処理、再資源化(販売)まで一貫したサプライチェーンを構築しており、品目ごとに主体が細かく分かれることもありません。
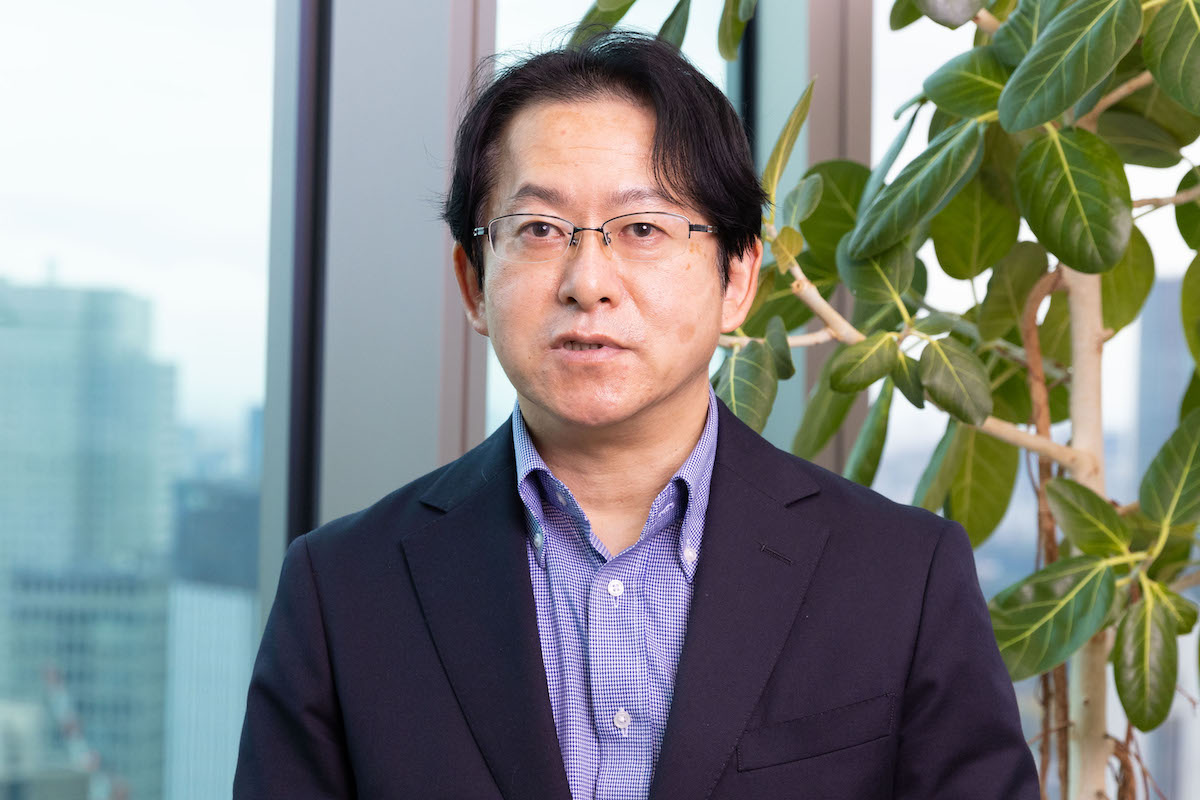
──現状メガリサイクラーが存在しない日本では、各企業はどのように対応していけばよいのでしょうか。
平沼:もちろん、中心となるメガリサイクラーが現れ、リサイクルがきちんと産業として成り立つことが理想ですが、日本においては難しいかもしれません。それよりも、再資源化可能な資源を排出する企業同士で連携し、一緒に廃棄物を集めて再資源化する体制を構築するといったボトムアップのやり方の方が、スムーズに進むのではないかと思います。
再エネ普及のポイントは自動車用の蓄電池
──日本全体でサーキュラーエコノミーへの転換を進めていくうえで、他に注目すべきポイントがあれば教えてください。
平沼:私の個人的な考えですが、最大の戦場となるのは電気自動車(EV)用の蓄電池でしょう。
気候変動問題への対処として再生可能エネルギーの普及が求められていますが、再生可能エネルギーは気象条件によって発電が左右されるので需給調整を行う必要があります。例えば、天気が良くて太陽光電の電力が余った際には蓄電池に貯めたり、逆に曇って十分に発電出来ない際には貯めておいた電力を放電して不足を補うなどです。
こうした調整を行うには電力系統に大規模な蓄電池を設置することが考えられますが、それにはコストがかかります。そこで登場するのが急速充電設備などを介して電力系統(Grid)と繋がっている電気自動車(Vehicle)の蓄電池を活用して電気の充放電を行い、需給調整を行うV2G(Vehicle-to-Grid)です。
V2Gの導入が広がれば再生可能エネルギーの課題を解決し、さらに普及させることが出来ます。再生可能エネルギーの普及が進めば、再生可能エネルギーの電力で水を電気分解して製造するCO2フリーのグリーン水素、および水素を燃料にして走行する燃料電池車(FCV)の普及にも繋がります。また、水素とCO2から都市ガス原料の主成分であるメタンを合成することができますのでクリーンな燃料を得ることも出来ます。
──電気自動車用蓄電池の導入には、さまざまな効果が期待できると。
平沼:電気自動車用蓄電池はその効果から、世界で注目されています。すでに欧米や中国では電気自動車の普及が右肩上がりで進んでいます。例えば欧州では2018年の販売実績202,000台に対し、2021年は約6倍となる1,231,000台の電気自動車が販売されています。EUでは2035年以降はCO2を排出する内燃機関を搭載する車の生産を実質禁止することも合意されており、あと十数年で欧州に年間一千万台規模のEVの巨大市場が誕生することになります。
当然サーキュラーエコノミーの資源循環に則って電気自動車は生産・消費・再資源化されることになるので、電気自動車の再資源化ビジネスも今後主戦場となることが考えられます。
一方日本はというと、残念ながら電気自動車の普及で大きく出遅れています。2018年の日本の電気自動車販売台数は27,000台であったが、その後は伸びず、2021年は22,000台と欧米に比べ桁違いに少ないばかりか右肩下がりに減っているという現状です。
──蓄電池の分野でも同様の状況なのでしょうか?
平沼:蓄電池の分野でも大きくシェアを失ってしまったという事態が起きています。もともと日本は蓄電池であるリチウムイオンバッテリーに関して圧倒的なシェアを持っていて、2015年段階では車載用が約40%、定置用が約27%を占めていました。しかしそこから中国と韓国が台頭し、わずか5年でシェアが激減。今ではだいぶ勢いを失ってしまっています。リチウムイオンバッテリーは日本で開発された技術なのに、これは本当に残念でもったいないことです。
とはいえノウハウの蓄積は十分にあり、実は日本の再生可能エネルギー関連の特許数は世界一です。特に水素発電に使われる燃料電池に関する特許数は2位のアメリカの倍以上。こうした技術的な資源を活かして様々な効果を生み出す電気自動車からサーキュラーエコノミーを推進していくのはどうか、というのが私の見立てです。
実際に、電気自動車に使用されるリチウムイオンバッテリーの再利用化にフォーアールエナジーという会社が取り組んでいます。同社は日産自動車と住友商事が2010年9月に共同設立した会社で、2018年には日本初となるバッテリー再生工場を福島県浪江町に開所しています。使用済みのリチウムイオンバッテリーの回収から、再利用のための加工、販売まで手がけており、1つの品目に限られているとはいえ、サーキュラーエコノミーの仕組みのモデルとすることができます。
各地で芽生えるボトムアップの再エネ施策
──『資源争奪の世界史』では、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、サーキュラーエコノミーの体制を整えることと同時に再生可能エネルギーの導入の必要性も説かれています。
平沼:再生可能エネルギーに関しては、有望な事例が少しずつ生まれ始めています。たとえば、農地に約3メートル程度の背の高い支柱を立てて太陽光パネルを設置し、農業を行いながら発電も同時に行うという営農型太陽光発電など地域主体の再エネ事業がその良い例です。
千葉県匝瑳市の「市民エネルギーちばx」などは、荒廃農地含む農地活用など地域の再エネポテンシャルを堀り起こし、実際に地域と企業がコラボレーションして営農型太陽光発電に取り組んでいます。ちなみに、国内の農地面積(荒廃農地含む)のうち約2%にあたる10万haに営農型太陽光発電を導入することで農作物の生産を損なうことなく、年間1,000億kWhの電力生産を確保することが可能という試算もあり、再生可能エネルギーの適地が少ないとされる日本においても大いに期待が出来ます。

他にも洋上風力発電など、日本のポテンシャルを活かした再生可能エネルギー施策は少しずつ芽が出始めている段階です。このように再エネ需要を地域で担う取り組みが日本中に広がっていけば、企業は脱炭素経営を実現でき、自治体も自分たちの地域でエネルギーを賄うことができるでしょう。
──決して悲観する必要はないと。
平沼:1つのスキームですべてが一気に動くヨーロッパと違って、日本では小さな有望事例をバージョンアップしたり、モデルケースとしてあらゆる業種へと転用したりしていくことで徐々に新たな仕組みが浸透していくという印象があります。まずは各地域の自治体を中心に小さなエネルギー循環の仕組みを構築して、そのモデルをもとに企業間の連携を拡大させる。さらにはそこから業種間の連携や政府などとの連携へと発展させていく――そんなボトムアップのやり方が、日本に合っているやり方なんじゃないでしょうか。
