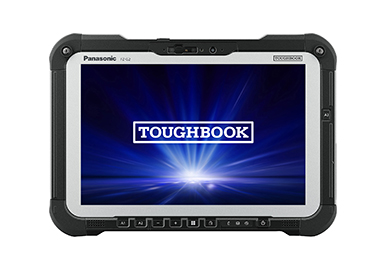コンシューマーグレードのタブレットの弱点をどうやってクリアするか。
「頑丈性」「バッテリー性能」「Windows OSへの対応」の3つの課題と向き合う。
象印マホービン様では、物流現場に運⽤デバイスとして、⻑年、他社製のコンシューマーグレードのタブレットを使⽤されて来られました。タブレット端末の使⽤シーンは、⼊荷時の検品・格納、出荷時のピッキングや仕分け前・積込前のチェック、在庫移動時の在庫検索、棚卸時の実棚⼊⼒など、多岐に渡ります。10年近く使⽤されてきたなかで、今回タフブック導⼊を統括された⼤窪様は、課題感は3つあったと語ります。
「⼀つ⽬は、頑丈性の問題です。物流現場ではタブレット端末を⼿に持ちながら作業することが多く、フォークリフトに端末を乗せて操作するシーンも頻繁にあります。物流センターの床は硬いコンクリートなので、タブレットを落下させてしまった場合の破損リスクを常に想定しなければなりません。コンシューマーグレードのタブレットはどうしても頑丈性の⾯で課題があり、落下させてしまうと液晶フィルムを貼っていても画⾯が割れてしまうことがありました」と頑丈性の問題を第⼀に挙げられました。
「⼆つ⽬は、バッテリー寿命の短さ。現場からは、バッテリー寿命の短さや充電トラブルが業務効率に影響しているという声が多く聞かれました。冬場は倉庫の気温が0度になることもあり、充電⾃体がうまくできず、作業員が朝出勤してタブレットの電源を⼊れようとしても⽴ち上がらないため、気温が上がってタブレットが起動するまで作業が進まないということもありました。バッテリーが劣化した端末は午前中には充電が切れてしまう状況で、いつの間にかすべての端末でモバイルバッテリーを使⽤することが当たり前の状況になっていました…」と、本来必要ではなかったモバイルバッテリーを追加で持ち運ぶことで、操作時の煩わしさが増えたといいます。
「三つ⽬は、OSアップデートの問題です。Windowsではない別OSのバージョンアップは社内での対応が難しく、外部委託先に依頼することになるため、⼀度の対応で『数百万円単位』の経費が発⽣している状況でした。それに加えて受⼊テストや委託先業者様との打ち合わせ、⾒積算出依頼、発注作業などの⼯数的な負荷も増え、OSのバージョンアップ対応だけで年間で2〜3週間ほど⼿を取られていたように思います。また、以前使⽤していたタブレットは古い世代のもので、最新のセキュリティパッチが当てられないというセキュリティリスクも残っていました」とセキュリティ⾯での課題も指摘。このような3つの課題を背景として、新たなデバイス導⼊の検討を開始しました。


現場の意⾒を尊重し、使い勝⼿や安全性にも配慮。
物理ボタンやバーコードリーダーなどの利便性が評価のポイントに。
今回、タフブックFZ-G2を導⼊する決め⼿となったのは、「頑丈性が⾼い」「⻑時間駆動&バッテリー交換可能」「OSがWindows」の3つすべてを⾼いレベルでクリアできていたからとのこと。
物流現場リーダーの宮⽥様は、導⼊決定においては現場の意⾒を重視したといいます。「各責任者が現場の声を吸い上げ、ミーティングを繰り返して『現場にとって本当に必要な機能・仕様は何なのか』を議論しました。そのやりとり回数は10回を優に超えると思います」という⾔葉からはタブレット選定における本気度が伺えます。意⾒交換を⾏ったからこそ⾒えてきた現場のニーズもあり、「⼿袋をつけたままでもタッチ操作ができる」「タブレットなのに物理ボタンがあってスピーディーに操作できる」の2点は、特に現場に刺さった部分だったそう。
「物流の現場では段ボールを取り扱う機会が多く、それらを素⼿で扱うと段ボールの鋭利な端で指を切るリスクがあります。従業員の安全を確保できることは⼤事なことですので、⼿袋をつけたままでも画⾯操作できるのは⼤きなメリットでした。物理ボタンについては、バーコードリーダーやカメラを即座に起動できるのが現場から⾮常に好評で、『商品事故があった際に素早く現場撮影ができます』と評価をいただいています」とタフブックの使い勝⼿の良さを語ります。また、他社タブレットを使⽤していた際はケースやストラップは⾮純正品を利⽤しており、使⽤時の落下・破損リスクが拭えない状況でしたが、タフブックは純正のショルダーストラップなどの周辺パーツが充実していることもポイントのひとつだったとのこと。「今までバーコードの読み取りには⼩型のスキャナをBluetooth接続で対応していたのですが、タフブックにはバーコードリーダーが搭載されているため、⼀台ですべてが完結するのもポイントでした」とタフブックの利便性も評価されました。




故障報告ゼロが物語る運用サイドの安心感に加え、コスト面でのメリットも。
タフブックFZ-G2を導⼊して半年ほど経過され、現在まで故障の報告はゼロ。「以前は2〜3か月に1台のペースで何らかの故障が起きていたので、それに比べると⼤きな変化」と宮⽥様は語ります。バッテリーの持ちも安定し、「業務時間8時間に対し⼗分な稼働時間が確保できる」という評価を現場の声としていただき、モバイルバッテリーを使⽤することもなくなり、現場のストレスも減ったそうです。
運⽤⾯でのメリットとして⼤窪様は、「Windows OSになったことでシステム管理ツールと連携し、アップデート管理やセキュリティ設定も簡単に。グループポリシーの⼀律配布もできるので、管理が⾮常に楽になりました」と、システム部⾨としての効果を実感されています。また、別の観点として「弊社では以前からパナソニック製のビジネスモバイルPCレッツノートを社⽤PCとして採⽤していたこともあり、今回のタフブック導⼊で、モバイル端末の問い合わせ窓⼝がパナソニック コネクトさんに⼀本化できたことも⼤きなメリット」といいます。情報システム部⾨の担当者にとって、問い合わせ窓⼝が⼀本化されることは意外と⼤きなポイント。故障やトラブルのたびに「どこの誰に問い合わせれば良いのか」と悩むこともなく、新しく着任した担当者でも迷わず問い合わせることができるため、⼼理的負担が圧倒的に削減されるといいます。

AI活⽤による需要予測データ取得でさらなる業務の最適化を。
タフブック導⼊を今後のDX推進の⼀歩としてとらえる。
今後は東⽇本配送センターでの導⼊実績をもとに、全社的な展開も視野に⼊れておられる象印マホービン様。現時点では、九州の物流拠点にも追加で10台導⼊予定、⻄⽇本の部品管理拠点にも11台導⼊をご検討中です。九州配送センターにおいては、初めてタブレット機器を導⼊することになり、今までのアナログ作業からデジタル化へ移⾏することで、現場のDX推進にも期待がかかるそうです。
⼤窪様は、今回のタフブック導⼊が全社的な業務改⾰や最適化への⼀歩になるとお考えで、「将来的にはAIを基にした需要予測データのリアルタイムでの確認など、タフブックはさらなる活用の可能性を秘めていると感じています。今後はこのタフブックを軸に、パナソニック コネクトさんが持つ多様な知⾒やソリューションと掛け合わせながら、現場のDX推進をより⼀層加速させていきたいと考えています。引き続き、パナソニック コネクトさんの提案に期待しています」とパナソニックと描く現場のDX推進の未来について語ってくださいました。

経営企画部システムグループ サブマネージャー<br>
⼤窪 真司様<br>

象印東⽇本配送センター<br>
リーダー<br>
宮⽥ 拓也様

※所属は納⼊時のものです。
象印マホービン株式会社様 事業紹介
「暮らしをつくる」を企業理念のもと、1918年の創業以来、魔法瓶の製造から始まり、今では炊飯器や電気ポットなどの調理家電製品や⽣活家電製品、リビング製品などの製造・販売を⾏っています。常に⽣活者の視点に⽴ち世界で信頼されている“象印ブランド”は、商品やサービスを通じて⼈々の⽣活を⽀えています。
所在地:〒530−8511 ⼤阪府⼤阪市北区天満⼀丁⽬20番5号
URL:https://www.zojirushi.co.jp/


物流センターの運⽤デバイスとしてコンシューマーグレードの タブレットを導⼊するも、頑丈性やバッテリー駆動時間、 OSアップデートのコスト増⼤に課題感。
頑丈性に加えて⻑時間駆動&バッテリー交換も可能な端末 の導⼊で、物流現場の業務を⼤きく改善。WindowsOS搭載可能により、IT運⽤に関わる負担を⼤きく軽減することに成功。
今回のタフブック導⼊は、物流現場の⽣産性向上だけではなく、現場の全社的な業務改⾰や最適化につながる⼀歩に。